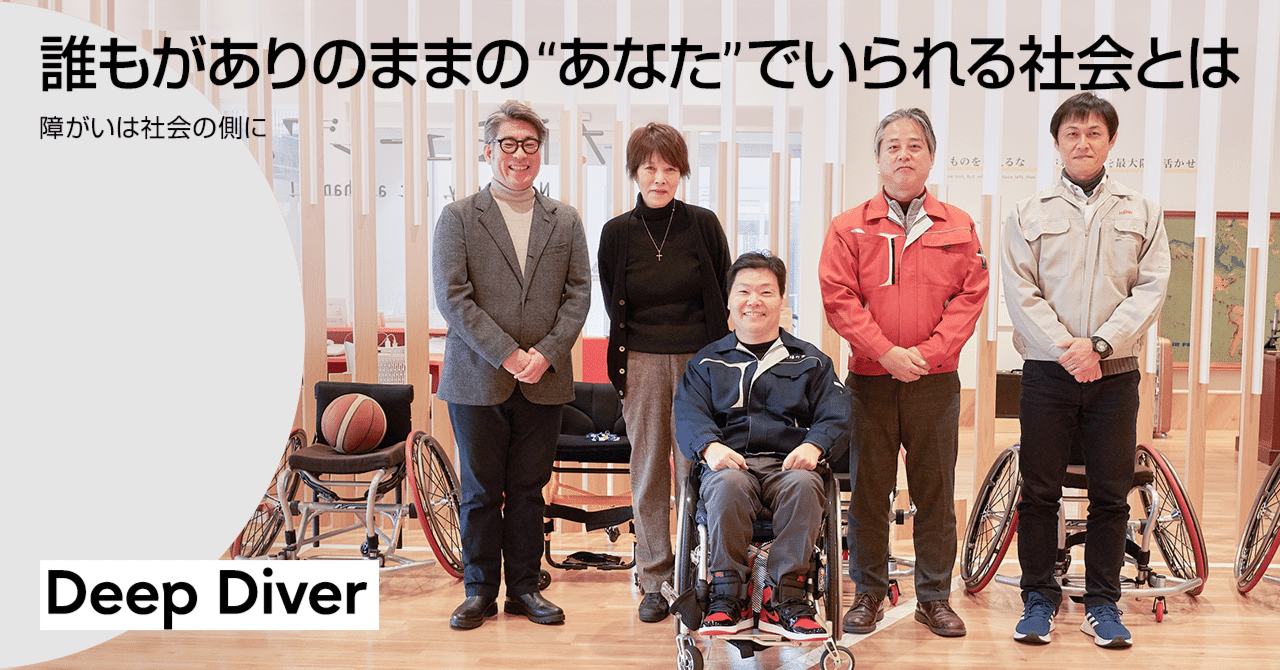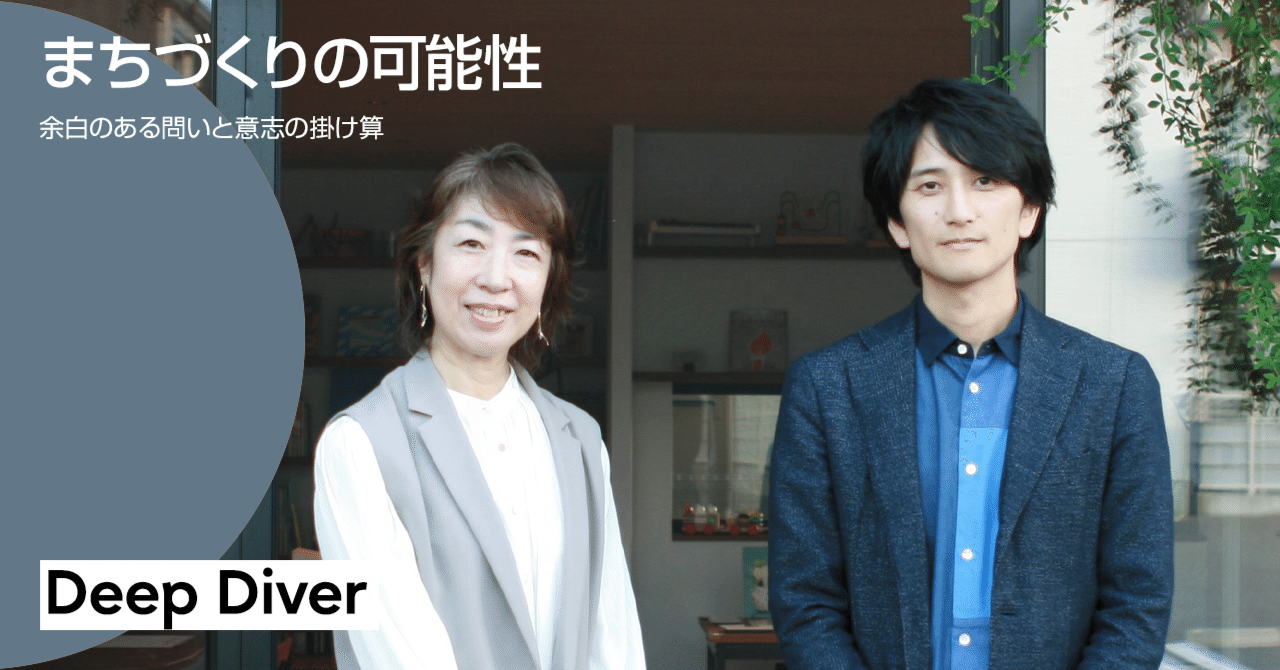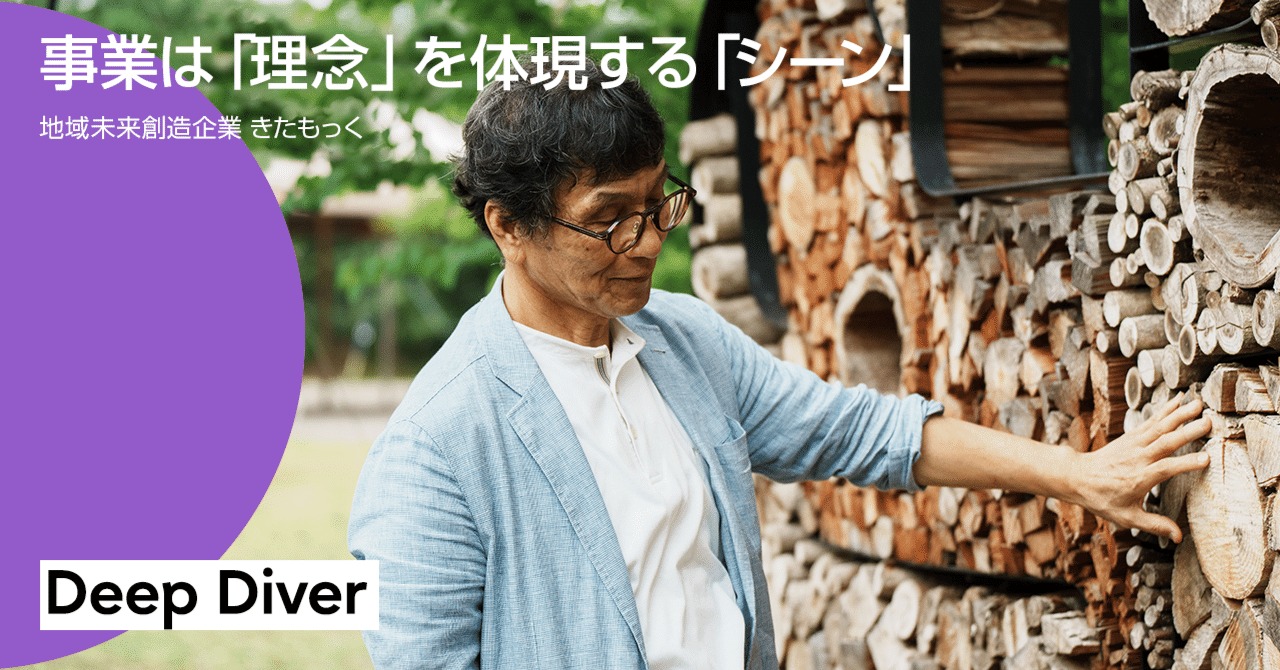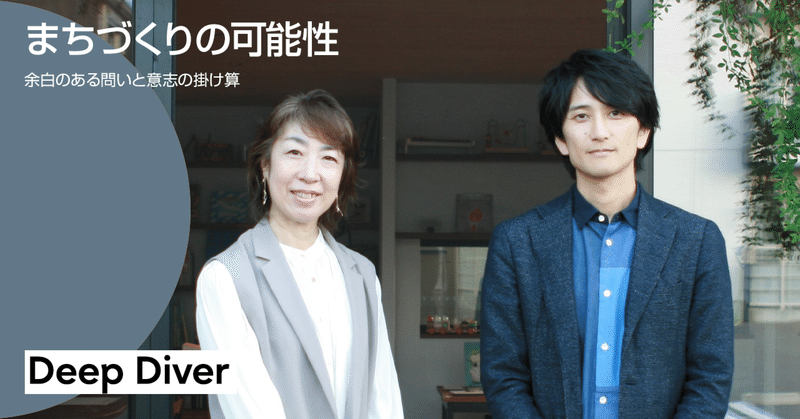DESIGN SPECTACLES
社会課題をいろんなメガネ(spectacle)をかけかえるように視点を変えて読み解き、問いを軸に組織を超えて繋がり共に社会を良くする。私たちはそのハブとなる活動体です◎富士通グループのソーシャルメディア公式アカウントのポリシーはこちら https://bit.ly/3G8pQgW
記事一覧

事業を通してサステナビリティを実現するヒントはどこにある?「SUSTAINABILITY TRANSITION BY DESIGN」公開
企業としてこれからの未来を考えるとき、社会課題解決と事業成長の両立は、重要なテーマです。しかし、実際にサステナビリティに取り組もうとすると、社内外に多くの課題があります。 富士通もそんな悩める企業の一つ。自ら実践したり、有識者と対話したりしながら、答えを探索し続けてきました。そして今回、そんな悩みを解消するヒントになりそうな仮説を「SUSTAINABILITY TRANSITION BY DESIGN」と題したレポートにまとめました。このレポートが、社会をより良くするための